
初訪問の方は、はじめまして。
他の記事から見てくださっている方は、こんにちは。
さらっと納得を目指す本サイト「さらとく」。
本日は第10回の記事となります。
前回の記事で書かせていただいた、年末に向けての「織田信長三本立て」計画。
今回は、その第2回です。
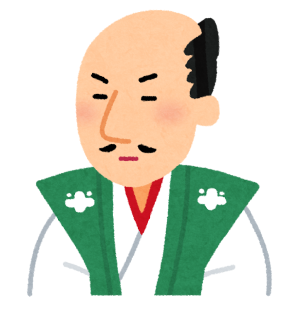
信長自身の人物像については前回まとめましたので、
今回は信長が勢力を強めたきっかけとなる戦いについてご紹介いたしますね。
逸話①:桶狭間の戦い(おけはざまのたたかい)
おそらく信長に関する戦いの中では
特に知名度の高い一件ではないでしょうか。
自領である尾張国を統一した後の、対外的な最初のピンチとも言われる戦いです。
「尾張国(おわりのくに)」というのは、信長の勢力があった土地のことです。
現在の愛知県のあたりになります。
おおまかな概要としては
大軍で攻め込んできた格上の大名を相手に
少数を率いた信長が奇襲をかけて、敵方の総大将を討ち取った
というものになります。
信長側にとっては、まさに大金星といえる戦果でした。
この一戦については、史実創作ともに色々な説があり、
・敵方に多くの悪条件(悪天候・兵の分散etc)が重なっていた
・下調べを重視した結果、隙が生じることを信長が見抜いた
・狙いやすそうな敵がいたから攻撃してみたらたまたま総大将がいた
等々、様々なバックストーリーが語られています。

ちなみに、信長本人は後世で

「いや、あれマグレだし」

と語ったという説もあるそうです。

大金星ではあっても、決して楽勝ではなかったんでしょうね。
逸話②:長篠の戦い(ながしののたたかい)
こちらも信長に関する戦いとして、
桶狭間の戦い同様に、非常に有名だと思われます。
有名なストーリーとして
当時、騎馬隊の強さで猛威を振るった敵を相手に、最新の武器である三千丁の火縄銃で対抗。
準備に時間がかかるという火縄銃の弱点を
「三段撃ち」という新たな戦法で克服し敵の騎馬隊を殲滅した。
のような展開が広く伝わっています。
ちなみに「三段撃ち」というのは、信長が考案したとされる火縄銃の運用方法で、
「弾を込めるのに時間がかかる」という火縄銃を効率的に運用するために考えられたそうです。
①火縄銃を持った兵を3組(グループA~C)に分ける
②グループAが火縄銃を撃つ(BとCは待機)
③グループBが前に出て火縄銃を撃つ(Aは後ろに下がって再装填、Cは待機)
④グループCが前に出て火縄銃を撃つ(Aは準備完了して待機、Bは後ろに下がって再装填)
⑤グループAが前に出て火縄銃を撃つ(Bは準備完了して待機、Cは後ろに下がって再装填)
⑤上記③~⑤を繰り返す

ただし、信長の逸話として非常に有名なこの戦法

現在では、後世の創作とされているそうです。

とは言え
・多数の火縄銃を用意したこと
・それによって敵に大打撃を与えたこと
については本当らしいですね。
以上、今回は信長の有名な戦いについて紹介させていただきました。
冒頭にありますように、今回は信長三本立ての第二です。
本年最後の投稿となる次回は、
織田信長の話題として避けて通れない最後の事件について
紹介させていただこうと考えています。
ここまでお付き合いいただきありがとうございました。
また他の記事でお会いいたしましょう。
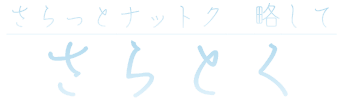











コメント